年の差夫婦が迎える定年後は、一体どんな生活が待っているのでしょうか?
23歳年の差結婚をした筆者は、年下妻として、主人の定年後に向けて今のうちから未来のことをしっかり考えておきたいところです。
健康面に注意することはもちろんのこと、定年後はお互いの役割分担など、年の差夫婦だからこそ向き合うべきテーマがあります!
年の差夫婦の絆を深めながら、幸せな老後を実現する秘訣とは?
年の差夫婦の定年後を真剣に考えた筆者の視点を、ぜひ一緒に覗いてみてください。
年の差婚すればもらえるお金「加給年金」を解説!

加給年金とは、65歳に達した厚生年金の受給者が配偶者や子どもなどを扶養している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される制度です。
加給年金は、扶養している家族がいる受給者の経済的負担を軽減するためのもので、いわば扶養手当のような役割を持っています。
ただし、扶養家族がいるからといって自動的に支給されるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
加給年金は厚生年金の仕組みの一部であるため、基本的には会社員や公務員など、厚生年金の加入者が主な対象です。
日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2つがあり、会社員や公務員は両方に加入していますが、自営業など厚生年金に加入していない人でも、過去の厚生年金加入期間が一定の基準に満たせば加給年金の対象となる場合があります。
「加給年金」をもらえる条件

加給年金をもらえる条件は、以下のとおりです。
- 共済年金を含む厚生年金に20年以上加入し、65歳に達していること
- 65歳時点で、生計を維持している(同居しており、年収が850万円未満)65歳未満の配偶者や、18歳の年度末までの子ども、または20歳未満で1級または2級の障害をもつ子ども
上記の条件を満たす場合、配偶者が対象となり、平均で年額約40万円が厚生年金に加算されます。
加給年金は年下の配偶者が65歳になるまで支給されますが、配偶者の年齢や収入状況によって受給期間が変動する可能性があるので注意が必要です。
加給年金は申請しないと受け取れないので、詳しくはお近くの「年金事務所」か「年金相談センター」で確認することをおすすめします。

主人は会社員&まだ子どもはいないから、65歳になったら加給年金が配偶者である筆者を対象にもらえるんだね!23歳年の差があるから、筆者が42歳の時からもらえるということか…これは助かる!!
年の差があるほど加給年金がお得に感じられますが、新たに国民年金保険料を納める必要も出てくるため、支給期間が長いとはいっても税負担があることも頭に入れておかなくてはなりません。
また、「年の差夫婦ばかりずるい」「独身世帯はもらえず不公平」などといった声もあり、加給年金の制度が改正される可能性もあります。
そのため、加給年金があるといってもアテにせず、自分でも老後に向けてお金を管理していく必要がありますね。
年の差夫婦が心配なライフイベントのお金3選


年の差夫婦にとって、将来を見据えた資金計画が必要です。
特に、住宅費や子どもがいる家庭は教育費、老後の生活費など、大きな支出をどう分担するかを話し合う必要があります。
年齢差によるライフプランの違いを考慮し、将来に向けて柔軟に備えていきたいものです。
以下、年の差夫婦が心配になるライフイベントのお金3選を、筆者の実体験も踏まえて解説します。
① 住宅ローンなどの住宅資金


年の差夫婦が住宅ローンを組む際は、返済期間や完済時の年齢制限に注意が必要です。
特に、働き手が高齢の場合、ローン期間を短くせざるを得ず、月々の支払いの負担が増える可能性があります。
定年後も無理なく返済できる金額を設定し、繰り上げ返済を活用するのが重要です。
また、60代以降の場合は、自宅を担保に借り入れが可能なリバースモゲージ型住宅ローンも選択肢に入れられます。
この仕組みを活用すれば、新築やリフォームの資金上達にも役立てられます。
② 子どものいる年の差夫婦は教育資金


年の差婚子どもを持つ場合、夫が定年退職した後に、子どもが大学に進学するタイミングが重なることがあります。
この時期には、教育費の負担が大きくなり、年金収入だけで住宅ローンや教育費をまかなうのは非常に難しいです。
そのため、夫が働いている間に、必要な教育資金を計画的に貯めておくことが大切です。
高校から大学卒業までにかかる教育費の平均が、約942.5万円とされおり、内訳は次のようになります。
- 入学費
- 授業料
- 教材費
- 塾費用
- 一人暮らしの場合の仕送り費
子どもの進路に応じた必要額を事前に見積もって準備することが求められます。
③ 配偶者が老齢になった時の老後資金


年の差婚における資金問題の主な原因は、一方の労働可能な期間が短いことにあります。
安定した老後を迎えるためには、住宅ローンや子どもの教育費に加えて、自分たちが生活するための資金も計画的に確保する必要があります。
収入不足を補うためには、以下で紹介する3つの対策が重要です。
年の差結婚で老後の生活に向けてできる3つの対策


年の差夫婦が定年後の収入不足を補填するためには、以下の3つの取り組みが必要となってきます。
- 年下女性も仕事をして家計の不安をフォローする
- 会社員の男性は65歳後の働き方を決めておく
- 退職金や年金に頼らず、支出を減らし貯蓄しておく
対策法について、順に確認していきましょう。
1.年下女性も仕事をして家計の不安をフォローする
年下の配偶者も仕事で活躍し、家計の支えとなることで、経済的な不安を解消できるでしょう。
年下女性の仕事による収入が家庭に安定感をもたらし、必要な支出にも余裕をもたせられます。
家庭全体のバランスを保ちながら、安心できる生活を支援することが可能です。
2.会社員の男性は65歳後の働き方を決めておく
会社員の男性は、65歳以降の働き方について早い段階で計画を立てることが大事です。
将来的な生活の質を維持するため、どのような仕事や役割を選ぶかを考える必要があります。
これにより、老後の不安が減り、健康的で充実した生活を送る準備ができるでしょう。
3.退職金や年金に頼らず、支出を減らし貯蓄しておく
退職金や年金に頼りすぎず、生活費を見直して支出を抑えることも大切です。
日々の節約を意識することで、将来のためにしっかりと貯蓄を積み重ねておけます。
節約や貯金などを継続して、経済的な不安を減らし、余裕をもった生活を維持する準備を整えましょう。
年の差夫婦の定年後は、収入への準備があれば問題ない!
年の差夫婦でも、定年後の収入にしっかり備えていれば、心配無用です!
早めに計画を立てて収入源を確保しておけば、年齢差があっても安心した老後が待っていると信じています。
貯蓄や投資で未来を守る準備をしておけば、心強いサポートにもなります。
準備が整っていれば、どんな時でも笑顔で暮らせる未来が広がるでしょう!
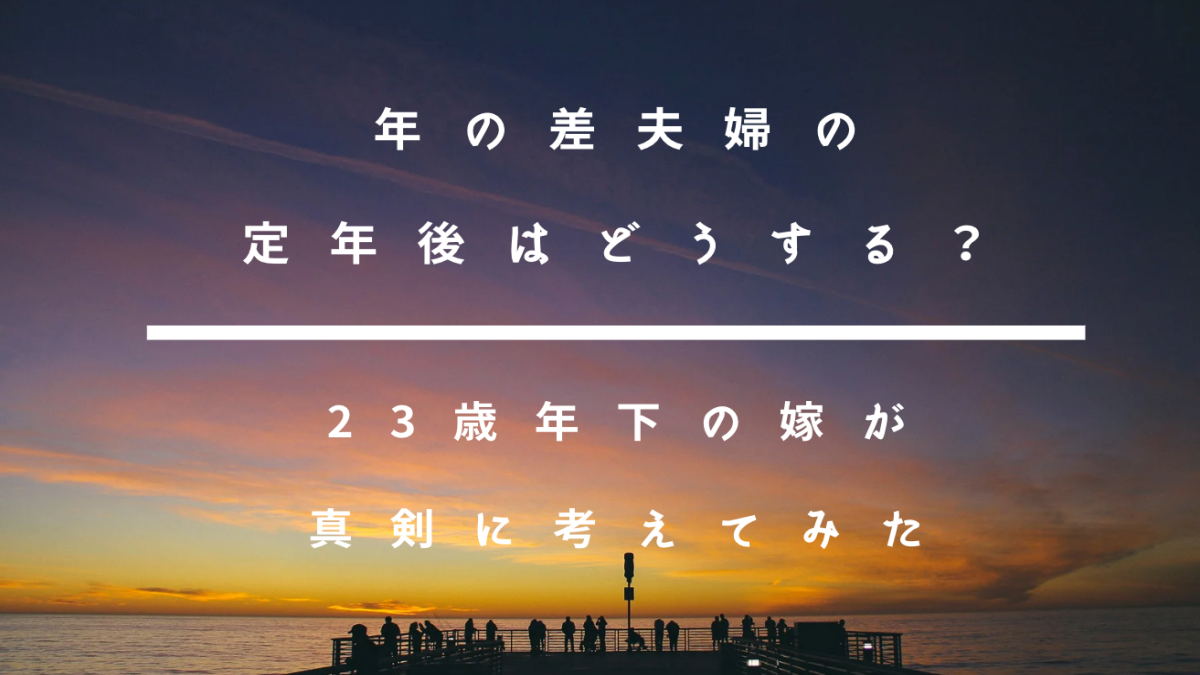

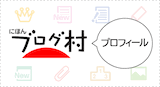
コメント